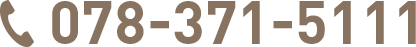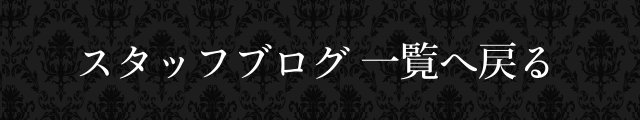歴史を感じながら🍁
2021/11/01 【神戸 結婚式場】 フォトグラファ
こんにちは。
11月に入りましたね。
早いものであと6日経てば11月7日は立冬ということで暦上では冬。
気温も低くなり紅葉も色づき始めていますね。
今の時期は紅葉を取り入れたロケーションフォトも人気ですが、
紅葉と聞いて思い浮かぶのが「紅葉狩り」ではないでしょうか

しかし改めて考えると紅葉狩りって、何で狩りっていうの?と疑問を感じませんか?
ということで本日は紅葉狩りの意味についてご紹介します。
まず紅葉狩りの歴史ですが、和歌集「万葉集」の中に『紅葉』や『黄葉(もみち)』という言葉が出てくることから色づいた紅葉を眺める紅葉狩りは約1200年前から存在していたと思われます。
紅葉というと非常に華やかな雰囲気ですが、当時の人々は紅葉の赤に無常(人生のはかなさ)を感じ、やがて訪れる冬の寂しさや紅葉した後に散る葉にわが身を重ねていたという説があります。

では現代のように紅葉狩りが世間一般に広まったのは江戸時代中期のころとされています。ちょうどこのころ、
伊勢神宮へお参りする伊勢講(いせこう)や熊野詣(くまのもうで)などの影響で庶民の間で旅行が流行しました。
その時に紅葉の木の下に幕を張り、お弁当やお酒を持ち込んでワイワイ盛り上がったともされていて、現代の花見の
ような感覚でしょうか?秋の味覚を楽しんだり、現代の紅葉狩りに近い形が作られたと言われています。
では本題のなぜ「狩り」と言う言葉が使われているかと言うと、
「狩り」とは本来、獣を捕まえる意味で使われていましたが、
平安時代は身近な環境に紅葉がなかったため、紅葉を楽しむ場合は山や渓谷に足を運ぶ必要があり、紅葉を見に出かけることを「狩り」に見立て、真っ赤に染まったもみじの木を手折り、実際に手に取って鑑賞していたといわれています。そこから紅葉狩りになったそうです。
古語辞典にも「狩り」は「求めてとったり、鑑賞したりすること」と記載されています。
ちなみに現代社会では実際に紅葉の木を折るという行為はマナー違反になるので行わないようにしましょう。
歴史背景を感じながら、紅葉も楽しんでみてはいかがでしょうか?
本日もありがとうございました。
フォトグラファー 池田