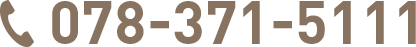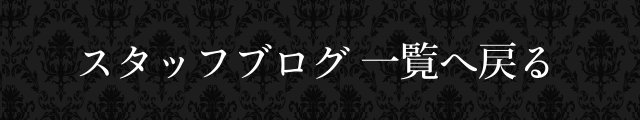七五三
2020/08/29 【神戸 結婚式場】 コスチューム
いつもスタッフブログを見ていただきまして
ありがとうございます。
コスチュームコーディネーターの山添です(#^.^#)
前回に引き続きお祝い事の由来について第2弾!
本日は七五三です。
医療の発達も未熟な時代では、子供の死亡率が
とても高く、「7歳までは神の子」と言われていて
当時、7歳まで元気に成長することは当たり前では
ありませんでした。
平安時代に宮中で行われていた3歳・5歳・7歳の
行事が基礎となり江戸時代に武家や商人の間で広まり
明治時代に「七五三」と呼ばれるようになり
大正時代に現在の形になりました。
七五三の起源になった行事とは以下の3つです。
・3歳「髪置きの儀」
生後7日目に頭髪を剃り、3歳迄は丸坊主で育てていましたが
3歳の春頃に髪置きの儀を行い髪の毛を伸ばし始めました。
成長を祝い健康な髪が生えてくると信じられていたためです。
3歳までは丸坊主で育てて頭を清潔にして病気の
予防にしていました。
3歳の春頃に儀式を行い、子供の成長を願い
髪の毛を伸ばし始めました。
・5歳「袴着(はかまき)の儀」
5歳になると当時の正装である袴を初めて付けて少年の
仲間入りをする儀式を経てから羽織袴を身に付けました。
現代の皇室でも数え5歳には「袴着の儀」が続けられています。
・7歳「帯解(おびとき)の儀」
着物を着る時に使っていた付け紐をとり、初めて帯を締める
儀式が9歳迄行われていましたが、江戸時代から男の子は5歳
女の子は7歳になると行うように変わりました。
それと11月15日に七五三のお祝いをするようになったのは
徳川家光が自分の子供、徳川綱吉のお祈りをした日が
この日で綱吉はその後、元気に育った事から11月15日は
七五三のお祝いをする日と定められたようです。
いかがでしたか。( ^)o(^ )
お祝い事の行事には、本当に深い意味がありますね!
また、ご紹介いたしますね~ (^O^)/