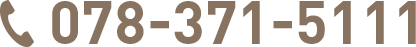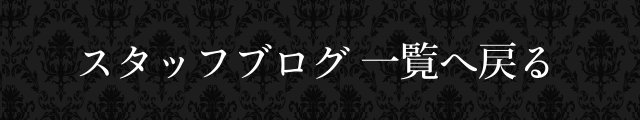結婚式にまつわる豆知識👰🤵💍⑩後編
2020/09/07 【神戸 結婚式場】 ウェディングプランナー
皆さまこんにちは😆❣️
いつもスタッフブログをご覧いただき
誠にありがとうございます😊💕
先日の、「結婚式の歴史 前編」は
いかがでしたでしょうか😊?
意外と知らなかった!という方も多かったのでは
ないでしょうか(*^^*)?
本日は前回の続き!明治時代以降の
結婚式の歴史をお話していきます❣️
✏️戦前〜終戦まで
戦前の日本では、結婚は家同士の結婚であり
親が準備するのが一般的でした。
花嫁両親が花嫁の幸せを願って豪華で立派な
結婚式を執り行いますが、幸せな結婚・幸せな花嫁に
つながり親からの愛情表現であると考えられていました。
多くの人が昔の結婚式は質素で慎ましく
行われていたと思いがちですが、
実は婚礼の義に3〜7日程度かけて、お金も
かなりかかっていたのです😳
終戦を迎えると法律で婚礼は制限されなく
なりましたが、
豪華に結婚式を挙げるだけのモノやお金がなく、
結婚式を挙げずに籍だけ入れる家庭も多くあったのです🤔
✏️そして現在
戦後になると、神の前で結婚を誓うだけではなく、
人前結婚式も広まるようになりました👰🤵
日本の景気が上がっていくと共に、ゲストが
楽しめるものに変化していきました✨
ゲスト軸で結婚式を行いたいという新郎新婦が増え、
式の形も随分と多様化し、オリジナリティのある
それぞれの結婚式が行われるようになりました💓
このように、結婚式のあり方や形は時代と共に
変化してきたんですね☺️✨
年代ごとに、結婚式や披露宴の内容や形も
全く違うので、そこも気になります…🤔
是非次回ご紹介できたらと思います😆❣️
最後までご覧いただき、
ありがとうございました(*’▽’*)🌟
ウェディングプランナー
木村 瑠里